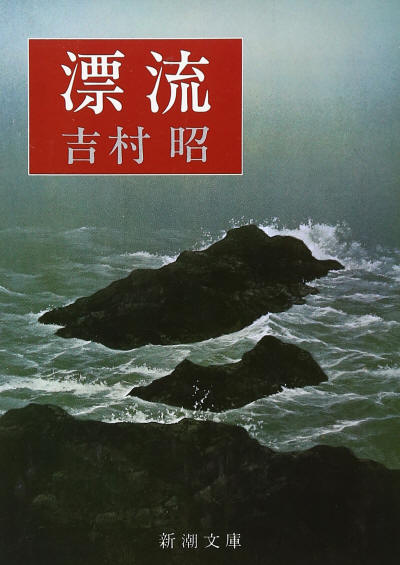吉村昭はおもしろいよ、と教えてもらったのがきっかけだった。
昔、さんざん読んだ吉村昭の小説。
歴史小説というのか、記録文学と言うのかわからないが、
昔の出来事を書いている。
今、何十年かぶりに、吉村昭さんの本を色々読み返す事をしている。
一行一行のなにげない表現を読むたびに、
この一行を書く為に、どんだけ資料を探して読んだ事か、
という思いで、吉村さんを一層尊敬する気持ちになった。
吉村昭さんは事実を羅列していくような書き方をする人だ。
事実ではない事をあまり付け足さない、そっけないくらいの文章を書く。
同じ歴史小説でも、司馬遼太郎さんだと、
想像力を働かせてかなり踏み込んだ表現をする。
例えば、その人物がどんな顔をしていたか、どんな声をしていたか、などまで表現する。
けれど、吉村さんの場合、あまり創作は付け加えずに書く。
例えば、当時の話し言葉はどうであったか、これは録音が残っている訳ではなく、
また、文書に残っているのは書き言葉のみなので、あえて現代語で書いている、
と、何かの記事で本人がそう言っていた。
そういう慎重な書き方がかえって信頼感を生んでいる様に思う。
歴史ドラマや小説では「〇〇でござる」とか言う事が多いけれど、
吉村さんは慎重に事実のみを追っているというわけだ。
ある会議が開かれ、出席者が続々と会場に集まった、という場面を書く時も、
その会議に出席していた人の名前を羅列する。
これを書くにはその資料や新聞記事などを読まなければならない。
また、夜間に製品を運搬する場面では、当時の街の様子や、
その夜の月齢はどうだったか、などを調べて書くことになる。
何階建ての○○ビルを通り過ぎると、三日月が低く輝いていた、
という一行を書く為には、かなり色々な資料を漁らなくてはならない。
自分も、古文書を調べて歴史小説を書いてみたいなあ、なんて思った事も有るが、
なかなかどうして、大変な事だ。
古文書と言っても、あっちこっち、多くの物を読まなければならなくなる。
書く以前に、それがとてつもなく大変な作業だ。
吉村さんは晩年、長く入院していたのだそうだ。
そして、娘さんに、「もういいよ」と言ったとのことだ。
「もういいよ」というのは、
もう、医療の機械を外してそのまま死ぬことを選択した、ということだ。
なんだか吉村さんらしい最後だったと思う。
そんな色々な思いでまた、吉村作品を読み返している。
吉村昭さんの教え
そばは5本ずつ食う
守っています(だいたい)